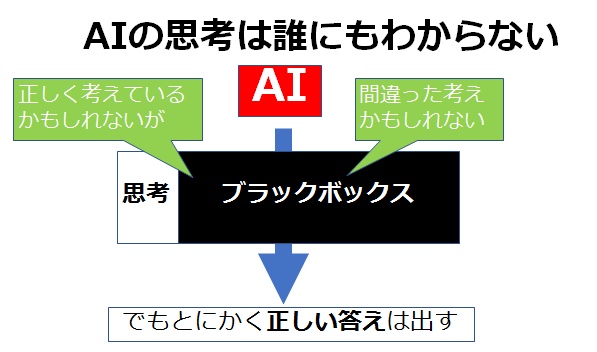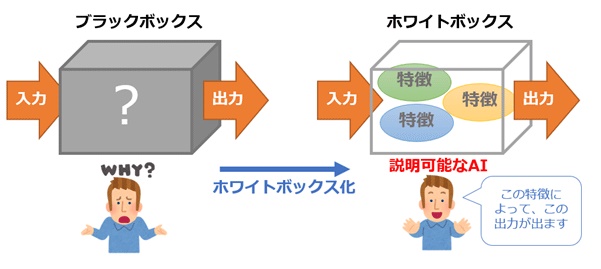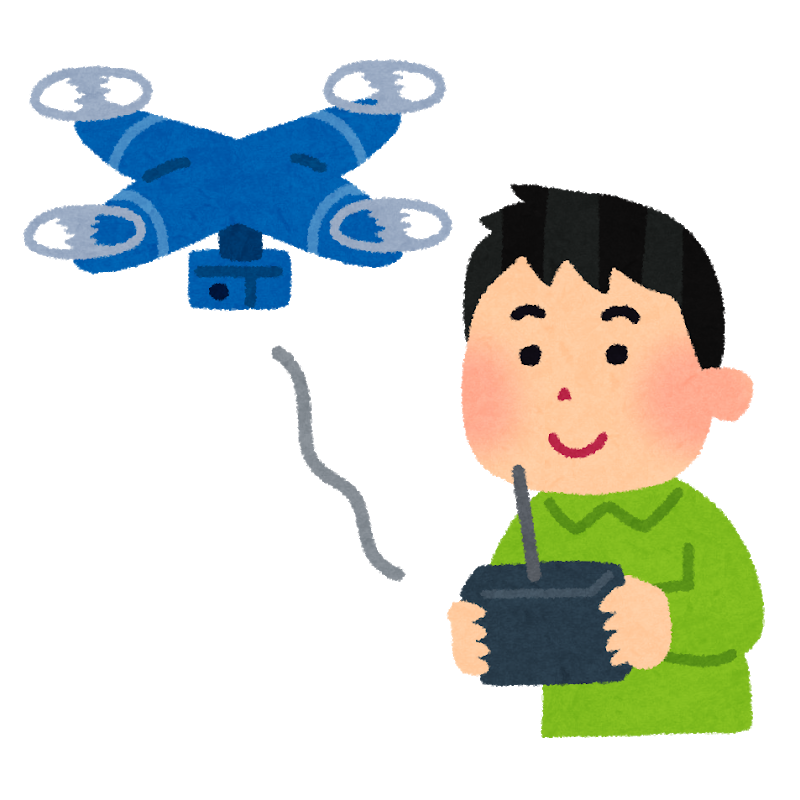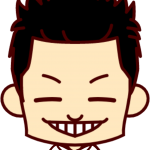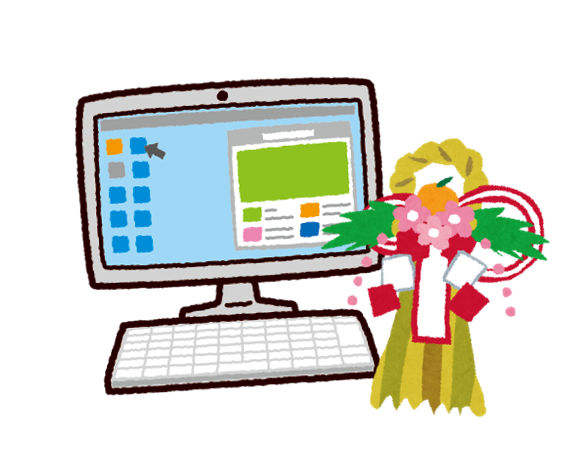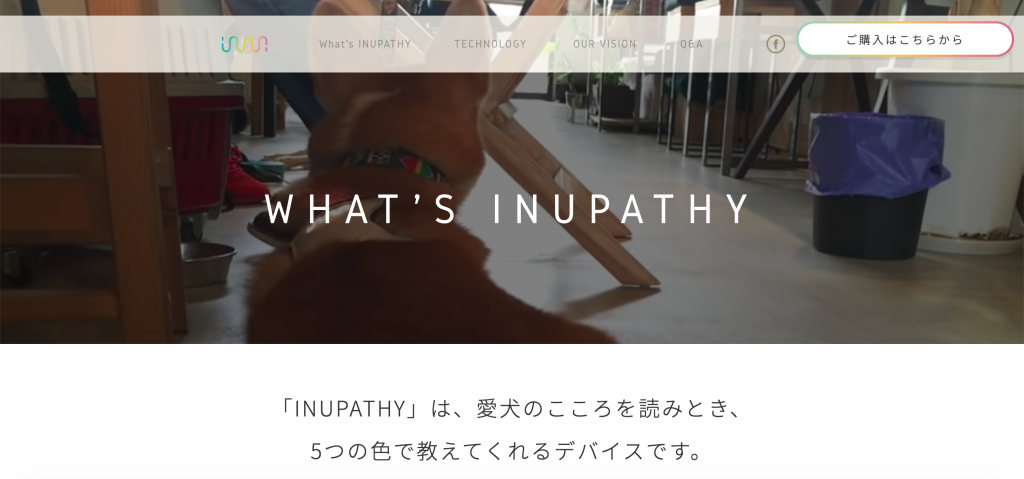「xTech」は、クロステックやエクステックと読みます。
分野・業界の名称○○と「Tech」(Technology:テクノロジー)をかけ合わせた言葉「○○Tech」で表現されます。
ひらたく言うと、「これまでの慣習に囚われずテクノロジーを活用してデジタルとリアルを融合した新たな価値を生み出す活動」的なこと。
【事例】
| EdTech(エドテック) | 教育×テクノロジー | オンライン学習,疑似体験(VR)学習 アダプティブラーニング, |
||||
| FinTech(フィンテック) | 金融×テクノロジー | 決済ペイ,仮想通貨,クラウドファンディング | ||||
| HelthTeck(ヘルステック) | 健康×テクノロジー | スマートウォッチ,消費カロリ-測定アプリ | ||||
| RetailTech(リテールテック) | 小売り・物流×テクノロジー | 無人店舗(amazonGo) | ||||
| AgriTech(アグリテック) | 農業×テクノロジー | スマート農業,農業IoT | ||||
新型コロナウィルス感染拡大の影響で、この数ヶ月間は、全世界の人々が行動規制を余儀なくされました。
”ステイホーム”が叫ばれる中で、インターネットの普及によるサービスやアプリ等のテクノロジーが、私たちの生活の支えになった事は言うまでもありません。
これからは更に、「テクノロジー」を企業や個人の活動基盤に取り入れて、新しい生活スタイルを築いていく事が未来のために大切なのだと思います。