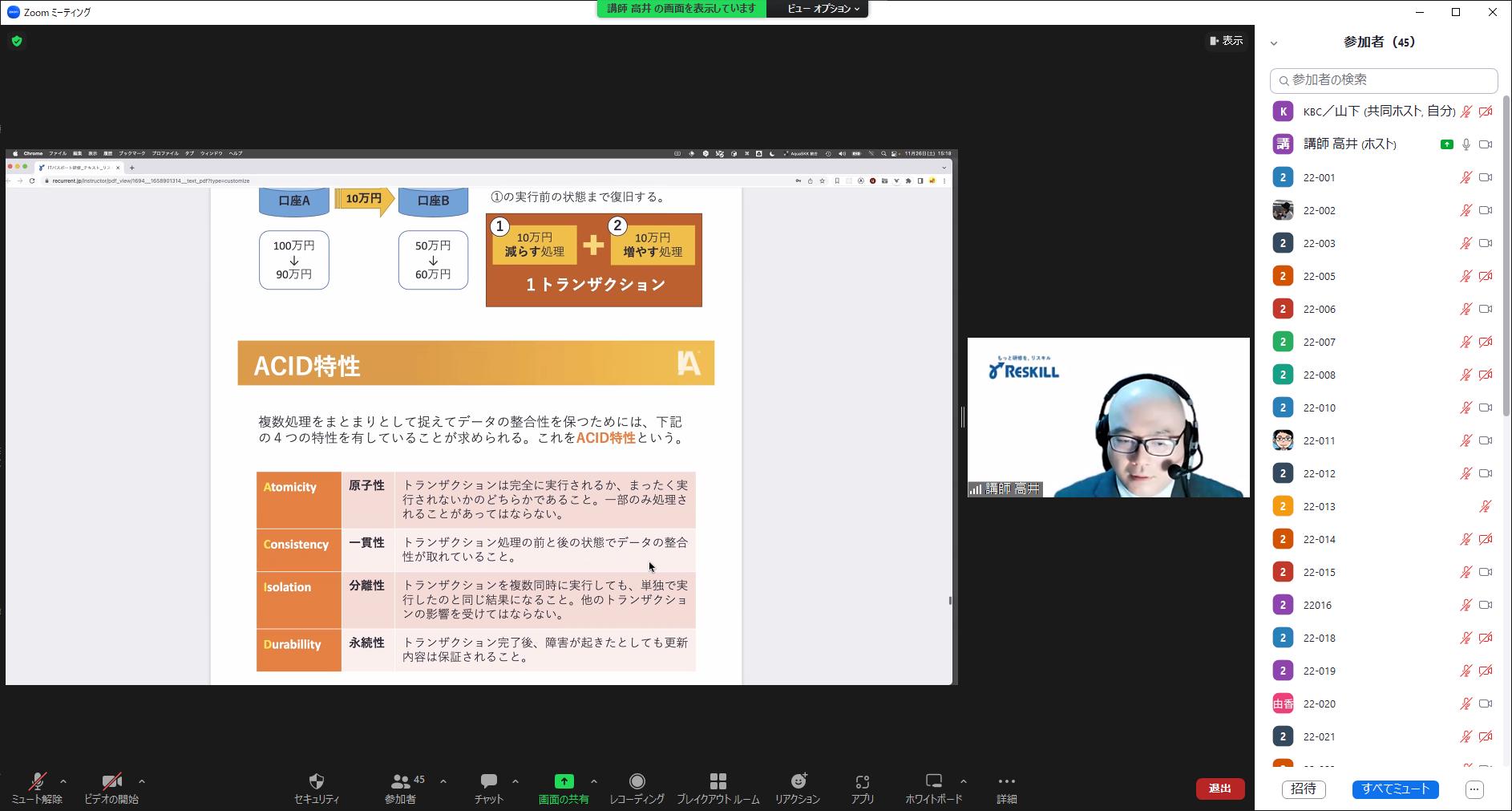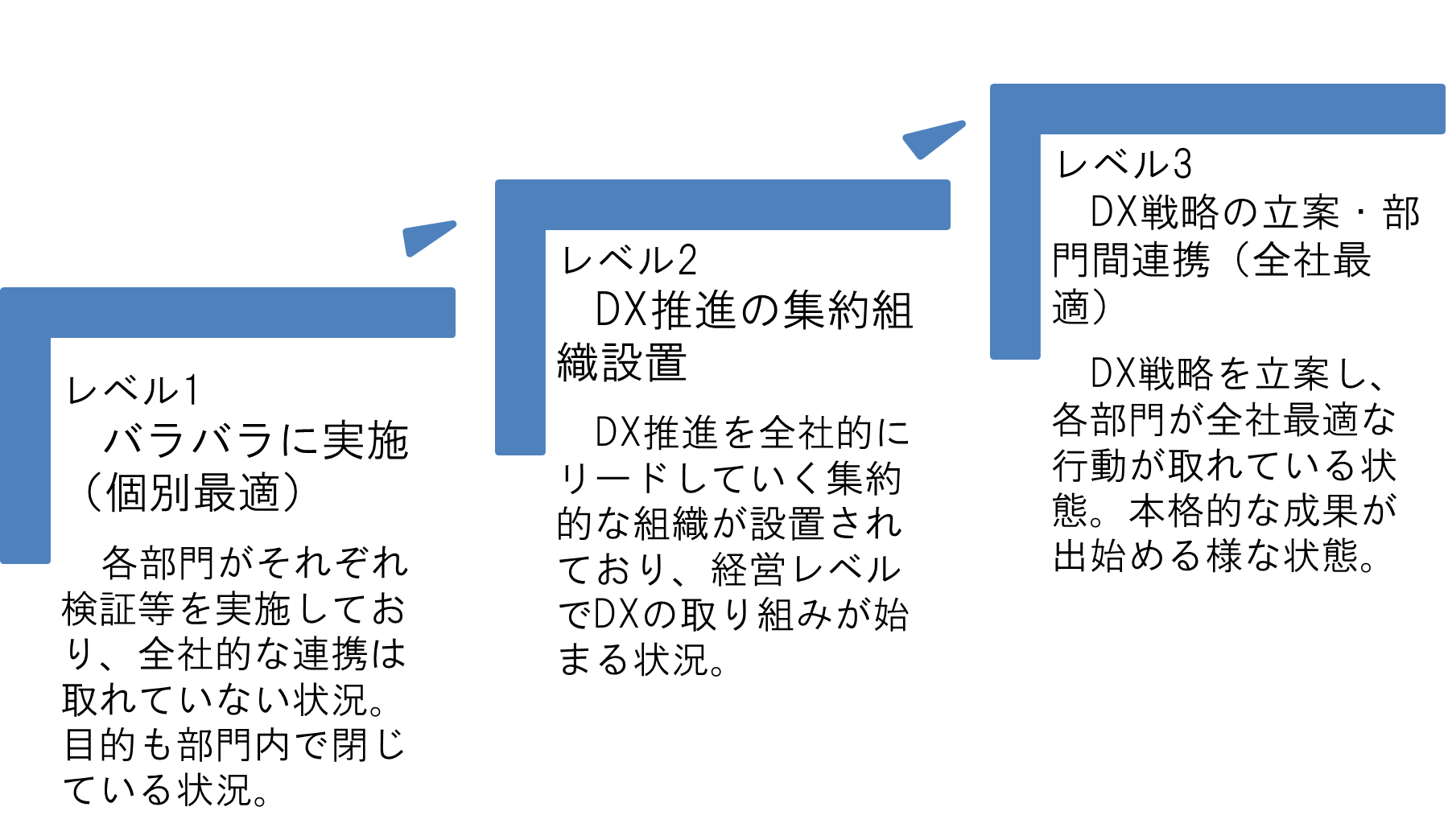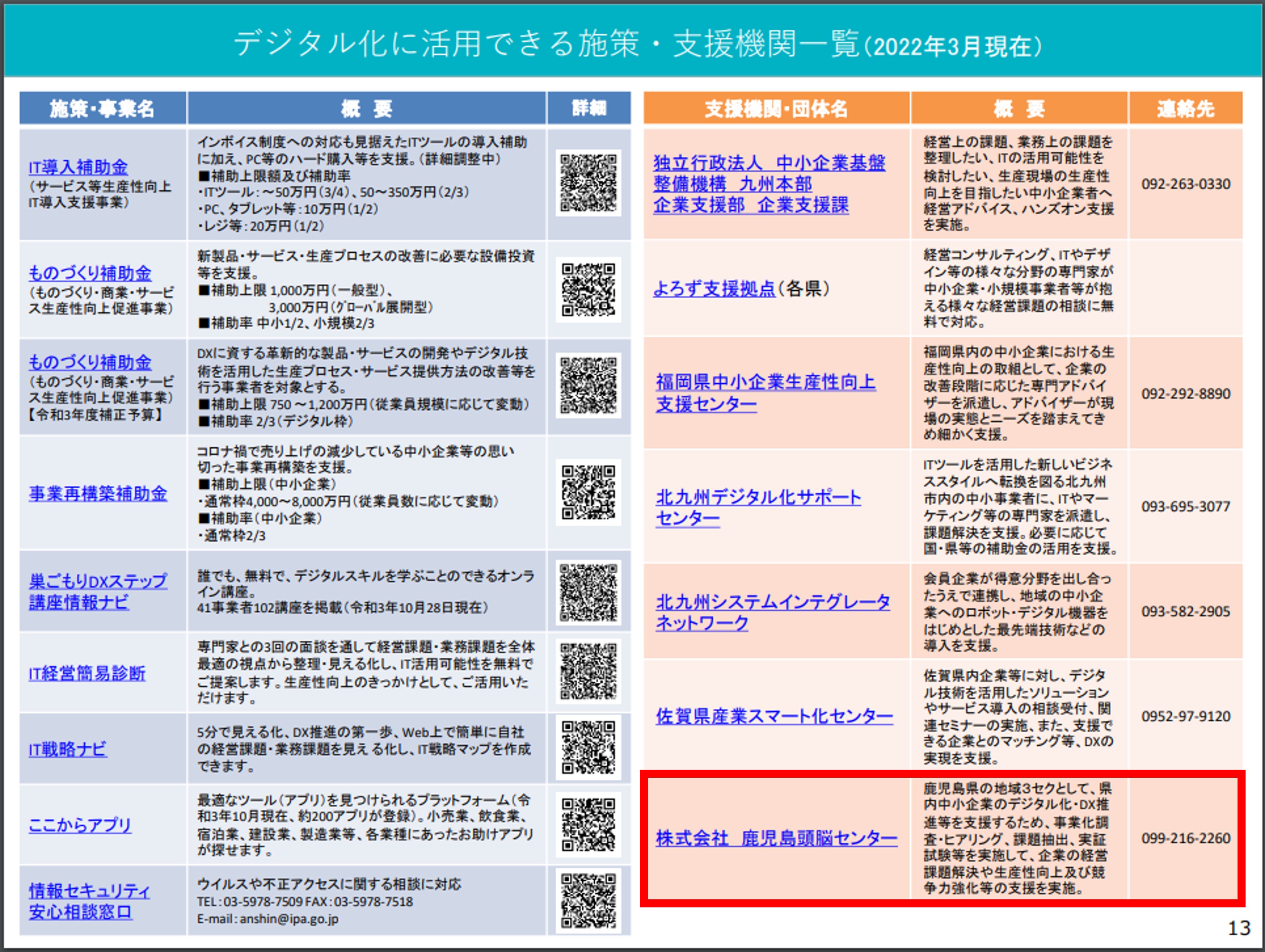下記日程で内閣府・経済産業省主催、鹿児島県共催の「S-NETセミナー2023 in 鹿児島」が開催されます。
日時:22023年1月17日(火)13:00~15:00(受付開始:12:30~)
内容:「衛星データ利活用の可能性について」
会場:マークメイザン ユーティリティスタジオA・B(鹿児島市名山町9-5)
★内容の詳細・お申し込みは,以下からお願いいたします。
「S-NET事業」
https://s-net.space/activity
「イベント詳細ページ(告知文)」
https://s-net.space/article/snet-kagoshima2023-01