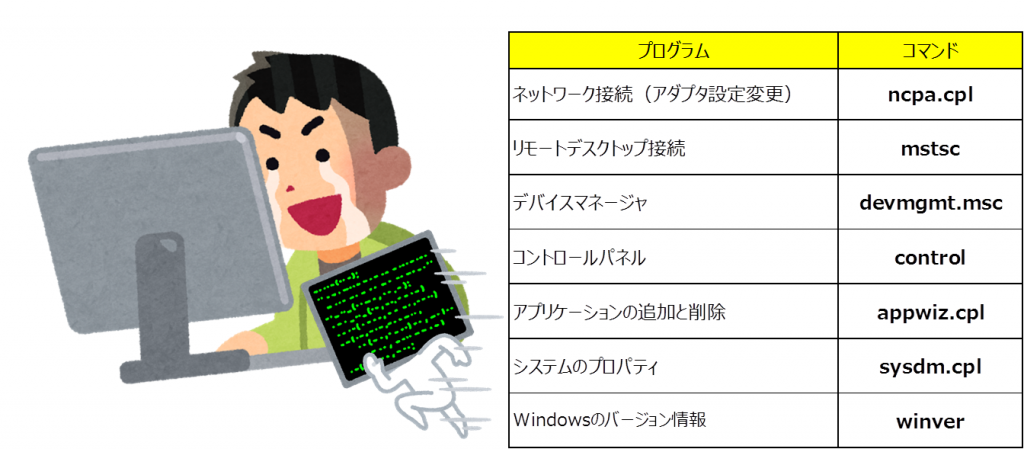2018年9月に経済産業省のデジタルトランスフォーメーションに向けた研究会の中間取りまとめとして『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』が公表さて以降、DX(デジタル トランスフォーメーション)という文字をよく見かけるようになりました。
DX(デジタル トランスフォーメーション)とは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義した概念です。
Digital Transformationなのに「DX」と略されるのは、「Trans」 で始まる単語の省略形として、「X」が代わりに使われるためです。
レポートには「複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが残存した場合、2025年までに予想されるIT人材の引退やサポート終了等によるリスクの高まり等に伴う経済損失は、2025年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)にのぼる可能性がある」と記載されおり、これを「2025年の崖」と呼んでいます。
初めて目にしたという方は、一読してみてはいかがでしょうか。自社と戦略や商機の一つになるかもしれません。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
出典
経済産業省
Wikipedia