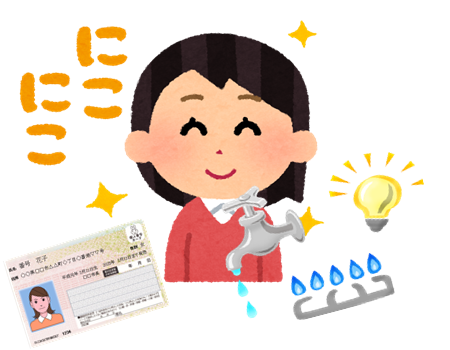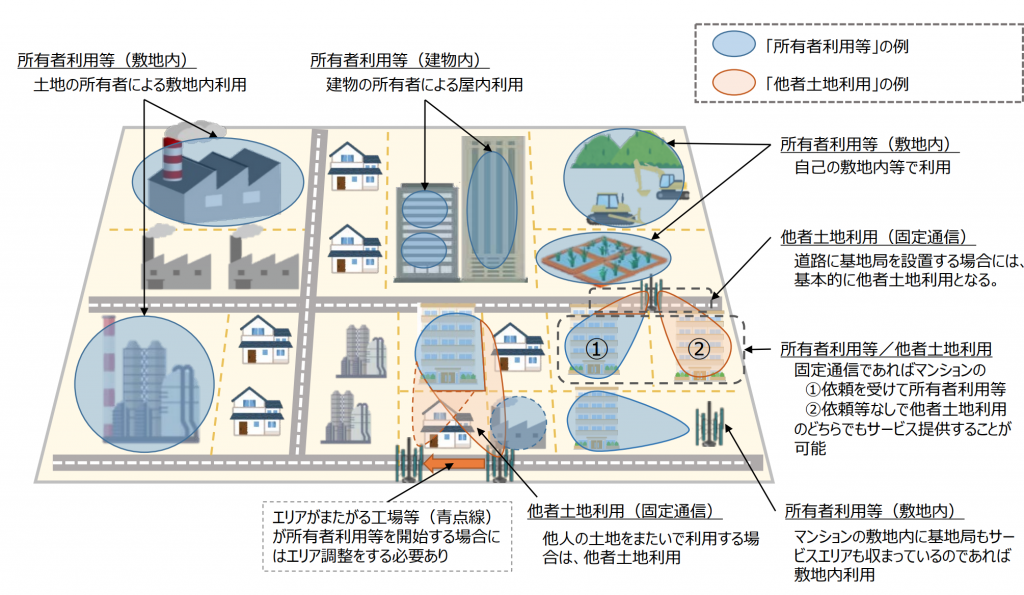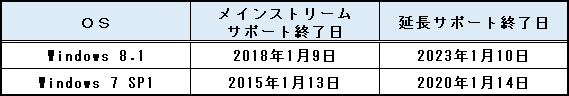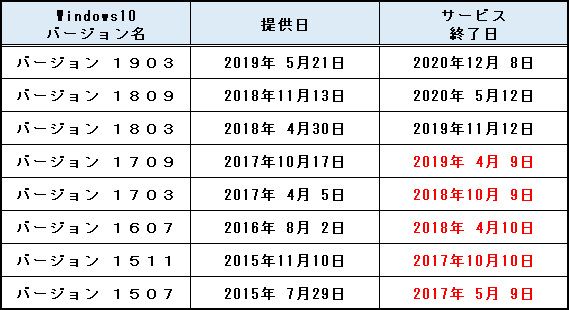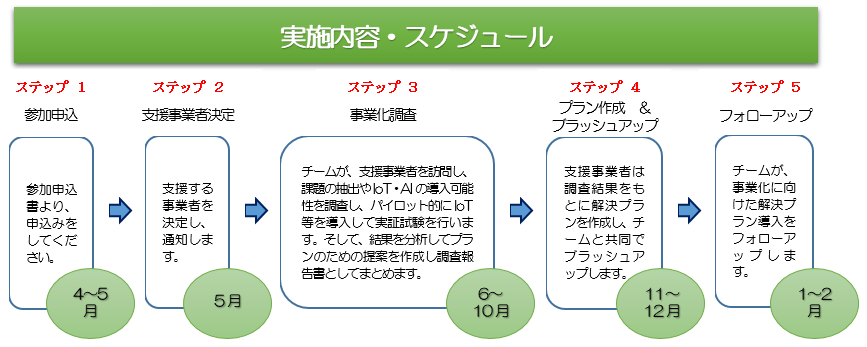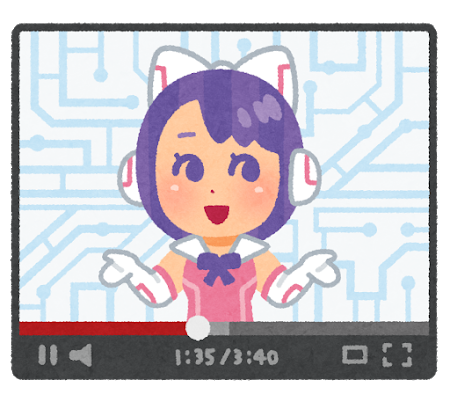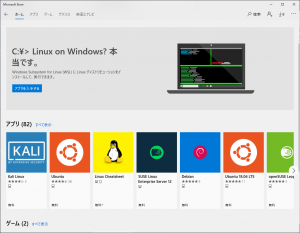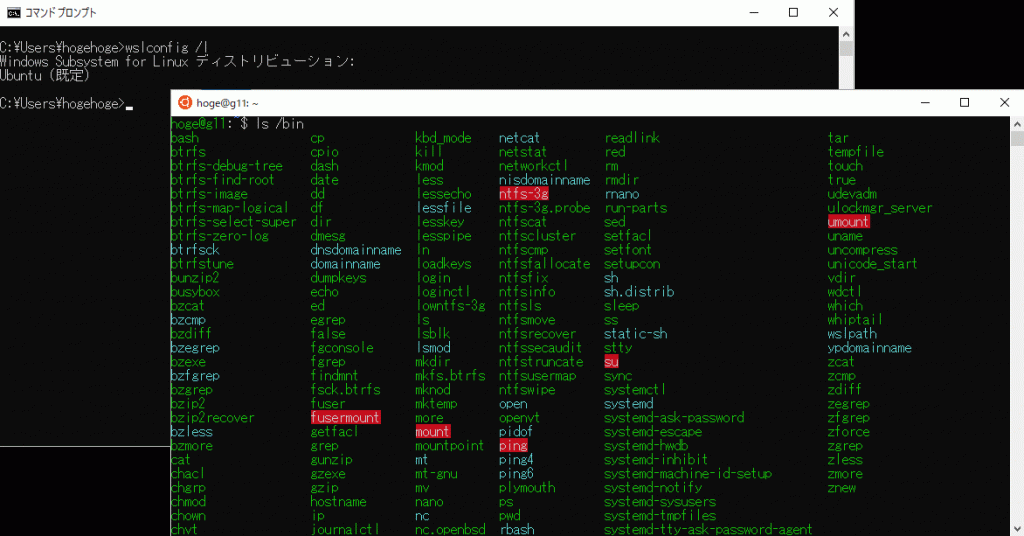実況 : 錦織、見事なバックのダウンザライン
審判 : フォルトー
実況 : 審判のアウトのジャッジに対して、錦織選手、チャレンジを要求です。
さぁ~、どうでしょう!?
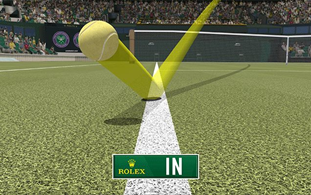
実況 : うぉ~ 入っている、インの判定です、ポイントは錦織選手に移ります・・・。
テニスのウィンブルドン選手権や全米オープンでよく見られるチャレンジのシーン。
チャレンジシステムとは、テニスなどの試合の最中に自分(又は相手)が打ったボールが
ライン際に落ちて、審判が出した判定に対して異議がある時に、ビデオ映像で判定を
行うシステムのことです。「ビデオ判定」とも言われます。
このチャレンジシステム、テニスの4大大会では、「全豪オープン」、「ウィンブルドン」
「全米オープン」で使われます。全豪、全米はハードコート(コンクリートでできたコート)
ウィンブルドンはグラスコート(芝でできたコート)で行われ、これらのコートではボールが
バウンドした跡が残らないためチャレンジシステムが使われます。
全仏オープンはクレーコート(赤土でできたコート)で行われ、クレーコートではボールの
バウンドした跡が残るため、目視判定となります。
チャレンジシステムの仕組みは、コートの周囲に設置された複数台のハイスピードカメラ
の映像がコンピュータで3D映像に変換され映し出す映像処理システムがコートの外で
動いています。ひと昔前までは考えられなかったハイテク技術がスポーツの世界を支え
ているんですね。来年の東京オリンピックが更に楽しみになりました。
サラ川柳風に ”言ったよね?”、 ん—っ、「ち、チャレンジぃ~」