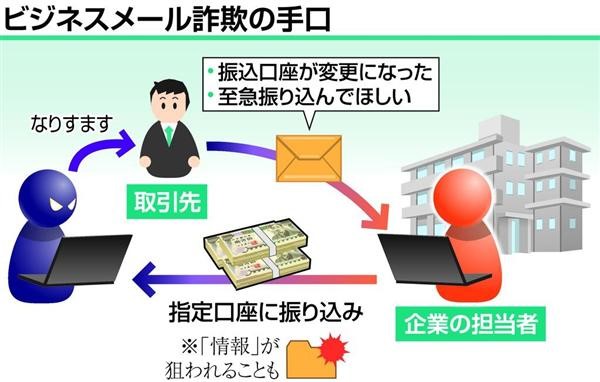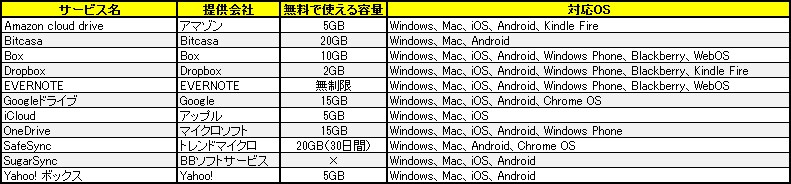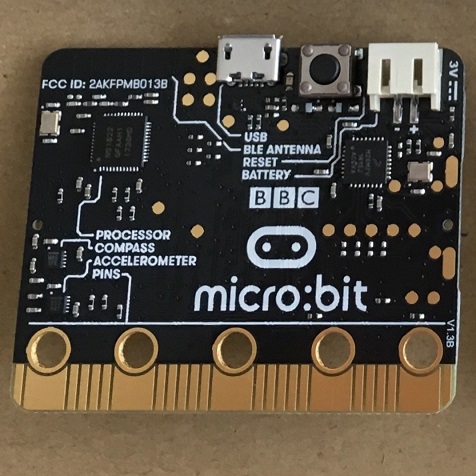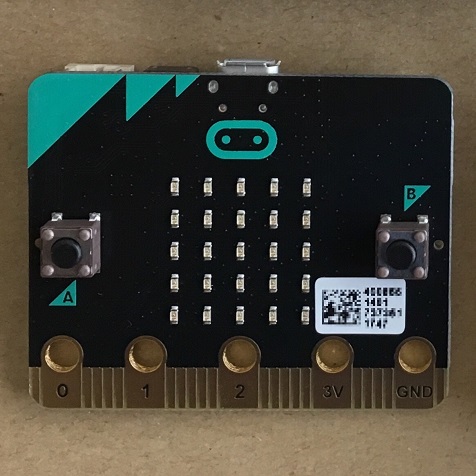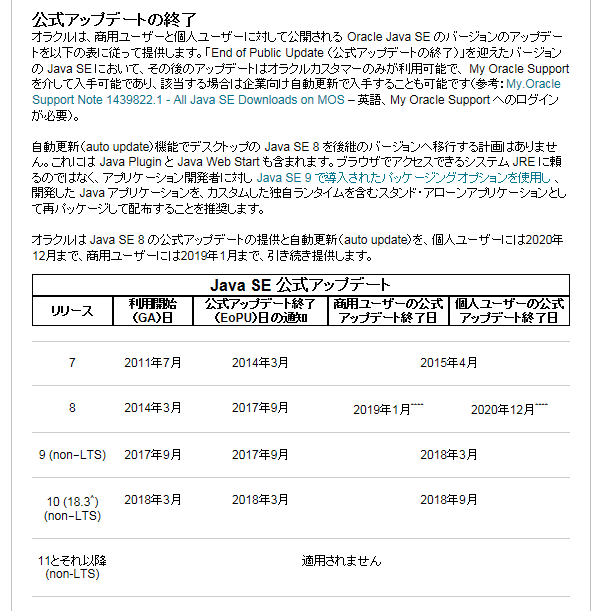最近、iPhoneの便利機能を悪用し不適切な画像を送る「AirDrop痴漢」が問題となっています。「AirDrop痴漢」の被害としては、ある日突然、バスや電車や人混みのの中などで
普通にiPhoneを使っていると、画面に突然不適切(卑猥)な画像がポップアップされます。
AirDropは、iPhoneのOSがiOS 7.0にアップデートされたあとにできたファイル共有機能で、メールやSNSなどを使わなくても写真や動画の送信が可能となってます。共有できるものには、写真・動画・URLやApp Storeのアプリなどがあります。iPhoneで撮影した写真をその場で友だちと共有できる便利な機能です。
AirDropでデータを送れる範囲は約9mですので、たとえば電車の中で「AirDrop痴漢」を行う人間には、共有可能な相手の名前しかわからないものの、嫌がらせ画像などを送ったときの反応で、本人と名前を特定される可能性があります。

「AirDrop痴漢」の被害を防ぐ方法としては、
①iPhoneの名前を変更して「AirDrop痴漢」の被害を防ぐ
・iPhoneの名前はAppleアカウントの設定などで登録した名前を使用して「〇〇(本人の名前)のiPhone」となるため、AirDrop使用時に、共有可能な相手としてこれが表示されます。そこから名前と、名前から性別までわかってしまう可能性があり、iPhoneの名称は、個人を特定されないものに変更するといいでしょう。
iPhoneの名前の変更方法は、[設定]>[一般]>[情報]>[名前]で確認、編集ができます。
②機能のオン・オフで「AirDrop痴漢」の被害を防ぐ
・iPhoneのAirDrop設定を「連絡先のみ」か「受信しない」に変更しておく方法です。
AirDropの設定の変更方法は、[設定]>[一般]>[AirDrop]でおこないます。
普段は「受信しない」設定にしておき、必要なときだけ「連絡先のみ」に切り替えて使うことが被害を防ぐ一番の方法だと思います。
AirDropはiPhoneのファイル共有を便利に使う機能ですが、一部の悪意ある人に悪用されることもありますので、被害に遭わないためにも、自分のiPhoneの設定を確認してみて下さい。
出典:https://time-space.kddi.com/digicul-column/digicul-joho/20180410/2295